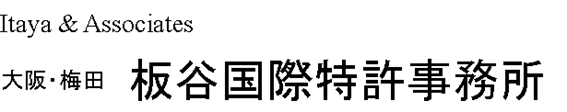01.マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願について
海外で商標登録するには、①各国に個別に直接出願する方法と、②マドリッド協定議定書に基づくマドプロ出願による方法とがあります。マドプロ出願は、自国(本国)の基礎登録・出願を基に、所定の願書(MM2という)を英語で作成し、本国官庁(日本特許庁)へオンライン提出します。願書には協定議定書の加盟国(114か国:2023年2月)のなか登録希望国を指定します。日本特許庁は願書を国際事務局へ提出し、方式審査を経て国際登録され、国際事務局は指定国官庁に通報します。国際登録の存続期間は、国際登録日から10年で、更新可能です。台湾は未加盟国です。
02.費用
国際事務局へ納付する政府関係費として、基本手数料903CHF、個別手数料例えばUSは388CHF等があり、日本国特許庁へ納付する手数料が9,000円です。例えば10ヵ国を指定した場合、政府関係費が概略40万円、代理人手数料が8万円程必要になります。
03.マドプロ出願のメリット・デメリット
複数国に対して一括出願であるため、多数の国で登録したい場合は、経費が節減できる効果があると言われています。しかしながら、マドプロ出願の政府関係費が結構高いことから、4ヵ国以上の国で登録を受けたい場合にのみ、マドプロ出願をお勧めします。また、指定国において拒絶理由が発見された場合、その国の代理人を選任して応答する必要があり、その費用が1ヵ国約10万円かかります。特に、米国では、日本登録時の商品・役務と同等の記載にしておいても、商品・役務の記載について具体性を求められることが多々あります。また、国際登録の日から5年以内に基礎出願が登録・更新されていないと、国際登録も取り消されてしまいます(セントラルアタックと言います)。なお、これにより商品(役務)の全部又は一部について国際登録が取り消された場合、名義人は、取り消された商品(役務)に関して指定国へ商標登録出願を行うことができます。
04.欧州連合商標(EUTM:旧CTM)との関係
マドプロ出願の際に欧州連合(EU)を指定することによりEUTM登録することができます。EUTMは、EUIPO(欧州連合知的財産庁:旧OHIM)における1つの登録で欧州連合(European Union)加盟国をカバーします(EU加盟国の3カ国以上に出願する場合はEUTMが有利と言われています)。EU加盟国のいずれか一カ国で商標を使用していれば不使用取消を免れることができます。EUTM出願が拒絶になるとEU加盟国全部にその効力が及びますが、拒絶がなかった国については通常の各国出願に変更することができます。EUTM出願は、相対的拒絶理由の審査をすることなく登録になりますので、同一・類似の商標が多く併存し、異議申し立てを受けることがあります。
お問い合わせはこちらより
ご連絡ください。